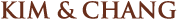|
|
|
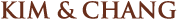 |
| Newsletter | September 2013 |
|
|
|
|
|
|
不動産 |
|
|
|
整理解雇における緊迫した経営上の必要性 |
|
|
|
大法院(最高裁判所)は2013年6月13日、自動車部品会社が2008年末のリーマン・ショックで全世界的に自動車需要が減少し、それにより当期純損失が発生している状況で2009年に実施した整理解雇が無効とした原審判決を破棄・差戻しする判決を言い渡しました。 |
|
|
|
上記事件の第1審及び原審は、整理解雇後に国が実施した税制優遇などの景気浮揚策を通じて会社の経営状況が一部好転した点等を上げ、整理解雇の要件のうち「緊迫した経営上の必要」が認められないと判断しました。 |
|
|
|
しかし、大法院は「整理解雇後の事情は、整理解雇当時の経営状態を判断する間接的要素として考慮する程度を越えて、整理解雇の正当性を判断する直接的な根拠とすることはできない」と判示し、(i)会社が経営難を克服するために休業、役員賃金削減、希望退職等の措置を施行した点、(ii)会社としては整理解雇当時、操業短縮等によって発生した余剰人材が短期間内に解消されると期待することは難しかった点、(iii)自動車部品製造業界の全世界的な景気が一層悪くなる見通しであった点等を理由に、整理解雇の必要性を肯定しました。大法院はさらに、企業の余剰人材のうち適正な整理解雇人員が何人なのかは原則として経営判断の問題に属するので、相当な合理性が認められる限り、経営者の判断を尊重しなければならないと判断しました。 |
|
|
|
当事務所は、原審である高等裁判所段階から会社を代理し、会計専門家の鑑定を申請するなど、多様な立証方法を活用して訴訟を遂行した結果、大法院で緊迫した経営上の必要性を否認した原審判決を取り消す結果を導き出すことができました。 |
|
|
|
本事件は、緊迫した経営上の必要性を判断する際は、整理解雇当時の会社の経営状態を基準としなければならないという既存の大法院の立場を再確認し、また、会社の経営状態を判断するに当たっては、外部専門家の鑑定結果が原則として尊重されなければならないという立場を明らかにしたという点でその意味があるといえます。 |
|
|
|
|
|
|