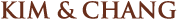|
|
|
|
|
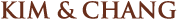
|
|
Newsletter | April 2015, Issue1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
税務
|
|
|
|
|
国外登録特許権の使用対価の源泉徴収に関する大法院判決
|
|
|
|
韓国大法院(最高裁判所)は、内国法人が米国法人との和解契約により国外にのみ登録された特許権の国外使用対価を支払った事例において、米韓租税条約の解釈により、国外にのみ登録された特許権の使用対価は、その特許権が国内で製造・販売などに事実上使用されたかどうかに関係なく、国内源泉所得に該当しないという判決を言い渡しました。これにより、国内源泉使用料所得から除外され、源泉税が還付されました。
|
|
|
|
大法院は、米韓租税条約第6条第3項、第14条第4項は、特許権の属地主義の原則上、特許権者が特許物を独占的に生産、使用、譲渡、貸与、輸入または展示するなどの特許実施に関する権利は、特許権が登録された国の領域内でのみその効力が及ぶとみて、米国法人が国内に特許権を登録して国内で特許実施権を持つ場合に、その特許実施権の使用対価として支払われた所得だけを国内源泉所得と定めたものであると判断し、2007年の大法院判決もこのような判断をし、国内未登録特許権の使用対価は国内源泉所得に該当しないという立場でした。
|
|
|
|
しかし、2008年12月26日の法人税法第93条改正により、外国法人が特許権を国外でのみ登録し、国内で登録していない場合でも、その特許権が国内で製造・販売などに使用されたときには、その使用の対価として支払われる所得を国内源泉所得とみる規定が新設され、韓国の課税官庁は、上記新設規定を根拠に、米国法人が国内に登録していない特許権の使用対価として受け取る所得に対して、源泉税を課税してきました。
|
|
|
|
このような状況において、大法院は、外国法人の国内源泉所得の区分に関しては、租税条約が法人税法より優先適用されると規定した国際租税調整に関する法律第28条により、特許権の使用対価が国内源泉所得に該当するかどうかは、米韓租税条約により判断されなければならないとみて、米韓租税条約の解釈上、国外にのみ登録され、国内には登録されていない特許権の使用対価は、その特許権が国内で製造・販売などに事実上使用されたかどうかに関係なく、国内源泉所得に該当しないという判決を言い渡し、従来の大法院判例の立場を再確認しました。
|
|
|
|
当事務所は原告である米国法人を代理し、特許権の属地主義、米韓租税条約の所得源泉規定の意味、租税条約と国内の税法との関係などを説明し、大法院から最終的に原告勝訴判決を受けることができました。
|
|
|
|
|
|
メインページ一覧
|
|
|
|
|