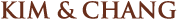|
|
|
|
|
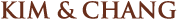
|
|
Newsletter | July 2016, Issue 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公正取引
|
|
|
|
|
不公正取引行為審査指針の改正及び施行
|
|
|
|
公正取引委員会は、不公正取引行為の類型及び基準を具体的に規定している「不公正取引行為審査指針」を2015年12月31日付で改正・施行しました。改正審査指針では、違法性の判断基準となる競争制限性の意味を明確にし、競争制限性に関する細かな判断基準が設けられました。また、不公正取引行為の個別類型については、抱き合わせ販売の違法性を競争制限性を中心に判断するよう修正し、取引上地位の判断基準を補完し、技術・人材の不当な利用・採用行為の違法性要件を緩和することを主要な骨子としています。
|
|
|
|
競争制限性の判断基準の具体化
|
|
|
|
|
改正前の審査指針は、不公正取引行為の競争制限性の意味のみを簡略に規定していましたが、今回の改正を通じて具体的な競争制限性の判断基準を設けました。
|
|
|
|
|
|
改正審査指針は、競争制限性の意味を「市場価格の上昇」または「生産量の縮小」と規定することによって、競争者の保護ではなく競争の保護が目的であることを明確にし、不公正取引行為について事業者が市場力(market power)を保有しているかどうかを判断してから、競争制限効果を立証しなければならないと明示しました。
|
|
|
|
|
|
市場力を保有しているかどうかは、事業者の市場占有率によって判断するように区分しました。例えば、市場占有率が30%以上の事業者は市場力を保有していると推定し、20~30%は市場集中度、競争状況、商品の特性など、様々な事情を考慮して判断するようにしました。10%以上は、多数の市場参加者が同じ行為をしてその効果が累積的に発生する場合に限って市場力が認められると規定しました。
|
|
|
|
|
|
改正審査指針は、このような一般的な競争制限性の判断基準を基に、特に単独の取引拒絶、差別取扱い、不当廉売に対して具体的な判断基準を提示しました。
|
|
|
|
|
抱き合わせ販売の違法性判断基準の修正
|
|
|
|
|
抱き合わせ販売は、主たる商品市場で相当な地位にある事業者が、従たる商品を抱き合わせて販売し、従たる商品市場の競争が制限される場合を規制するのが一般的な競争法理論ですが、改正審査指針は、主要国家の法執行の慣行である点を反映して、抱き合わせ販売の違法性の判断基準から不公正な競争手段である場合を削除し、競争を制限するかどうかを中心に違法性を判断することとしています。
|
|
|
|
|
|
これによって改正審査指針は、(1)主たる商品と従たる商品が別個の商品かどうか、(2)抱き合わせ販売をする事業者が、主たる商品市場で市場力があるかどうか、(3)主たる商品と従たる商品を一緒に購入するように強制するかどうか、(4)抱き合わせ販売が正常な取引慣行に照らして不当かどうか、(5)抱き合わせ販売によって、従たる商品市場の競合事業者が排除される、または排除されるおそれがあるかどうかを考慮し、抱き合わせ販売の違法性を判断するように要件を修正しました。
|
|
|
|
|
取引上地位の判断基準の修正
|
|
|
|
|
改正審査指針は、取引上地位の濫用行為で要求される事業者の取引上の地位に関する判断基準を補完しました。改正前の審査指針は、取引上の地位を判断するにあたって「取引相手方の代替取引先確保の容易性」を考慮しましたが、改正審査指針は、取引上地位が認められるためには、(1)継続的な取引関係が存在しなければならず、(2)いずれか一方に対する取引依存度が相当高くなければならないことを要件として規定しています。
|
|
|
|
|
|
また、改正審査指針は最近の判例を反映し、取引上地位の濫用行為の相手方は原則的に事業者に限定されると規定しました。ただし、不特定多数の消費者に被害を被らせるおそれがあったり、類似する違反行為類型が継続的・反復的に発生するなど、取引秩序との関連性が認められる場合には、消費者に対しても取引上地位の濫用行為が成立する可能性を残しておきました。
|
|
|
|
|
技術・人材の不当利用・採用行為の違法性要件の緩和
|
|
|
|
|
これまで一部では、技術・人材の不当利用・採用の違法性要件が厳しいため、企業がM&Aを活性化する代わりに、技術や人材を不当に利用または採用するという主張がありました。そのため、改正案は、当該行為の違法性要件を「著しく事業活動を困難にする場合」から「事業活動をかなり困難にする場合」に緩和しました。
|
|
|
|
|
|
今回の審査指針の改正により競争制限性の判断基準がより具体化し、違法性の判断基準が整備されることによって、公正取引委員会の不公正取引行為に対する法執行の一貫性が高まると予想されています。
|
|
|
|
|
|
|
|
メインページ一覧
|
|
|
|
|
|
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細については、弊事務所のホームページをご覧下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|