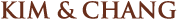|
|
|
|
|
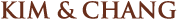
|
|
Newsletter | April 2015, Issue1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
証券
|
|
|
|
|
2015年の資本市場法施行令改正
|
|
|
|
資本市場法施行令の改正案が2014年12月9日に公布され、2015年1月1日から施行されています(ただし、年金基金の株主権行使の制限緩和条項は公布日から施行)。改正資本市場法施行令は、(1)上場企業関連規制の緩和、(2)資産運用業関連規制の緩和、(3)その他制度関連改正事項を含んでおり、主な改正事項は次の通りです。
|
|
|
|
電子的方法による委任状用紙の交付の容認など議決権の代理行使の勧誘規制の緩和(第160条第5号新設、第163条第1項第7号)
|
|
|
|

|
議決権の代理行使の勧誘のための委任状用紙などの交付方法として、従来容認されていなかったインターネットホームページを利用する方法を新設
|

|
電子的システムを利用した委任状用紙などの交付が可能なように法的根拠を設定
|

|
株主総会の目的事項の一部に対して、まず議決権の代理行使の勧誘ができることを明確にした。
|
|
|
|
|
自己株式で償還する償還社債に対する処分みなし規定の導入(第176条の2第4項)
|
|
|
|

|
交換社債の場合とは異なり、自己株式で償還できる償還社債の場合には、別途自己株式の処分みなし規定はなかったが、償還社債に対しても交換社債と同様に、社債発行時点で自己株式が処分されたものとみなすようにする。
|
|
|
|
|
株式買取請求権の行使により取得した自己株式の処分期限の延長(第176条の7第4項)
|
|
|
|

|
株主の株式買取請求権の行使により保有することになった自己株式の処分期限を株式の買取日から3年から5年に延長
|
|
|
|
|
上場会社の合併価額の算定に関する規制の緩和(第176条の5第1項第1号)
|
|
|
|

|
上場会社が他の上場会社と合併する場合、証券市場における終値を算術平均した価額を基準に30%の範囲(従来は10%)内で割引または割り増しした価額を合併価額として算定できるようにした。
|
|
|
|
|
年金基金の配当に関する株主権行使の制約要因の解消(第154条第1項第4号)
|
|
|
|

|
従来は、年金基金が企業の配当政策など主要経営事項に事実上の影響力を及ぼす場合、経営参加目的があるものとみなされ、持分変動公示特例、短期売買差益の返還の例外などの適用を受けることができなかったため、年金基金が配当に関連する株主権(株主提案、理事会に対する事実上の影響力の行使など)を積極的に行使できなかったが、改正施行令は、年金基金が企業の配当決定に事実上の影響力を及ぼしても、経営参加目的の投資でないものとみなす。
|
|
|
|
|
集合投資業者に対する経営実態評価の免除(第35条第2項第1号オ目の新設)
|
|
|
|

|
集合投資証券以外の金融投資商品に対する投資売買業または投資仲介業を経営しない集合投資業者に対して経営実態評価を免除するように規制を緩和
|
|
|
|
|
信託業者の退職年金に関する不健全な営業行為の禁止(第109条第1項第4号)
|
|
|
|

|
信託業者が「勤労者退職給与保障法」による特定金銭信託の信託財産で信託業者の元利金の支払を保障する固有財産と取引する行為を禁止する。
|
|
|
|
|
資本市場法付則により、上場会社の預託決済院のシャドーボーティングの廃止を電子投票の実施及び代理行使の勧誘を実施した会社に限って3年間猶予(資本市場法付則第18条)
|
|
|
|

|
シャドーボーティング(預託決済院の中立的な議決権の行使)を廃止する資本市場法の改正条項が2015年1月1日から施行されていますが、2014年12月30日付の付則新設により、電子投票及び議決権の代理行使の勧誘を実施した上場会社に限って、(1)監事及び監査委員会委員の選任または解任、(2)株主の数などを考慮して一定の基準に該当する法人の場合、株主総会の目的事項に該当する事項については、2017年12月31日までシャドーボーティングを活用できるようにしました。
|
|
|
|
|
|
|
|
メインページ一覧
|
|
|
|
|
|
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細については、弊事務所のホームページをご覧下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|