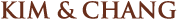|
|
|
|
|
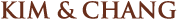
|
|
Newsletter | September 2014, Issue3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
環境
|
|
|
|
|
土地所有者の責任を合理化した改正土壌環境保全法
|
|
|
|
汚染土壌所有者の免責範囲及び責任限度の設定を骨子とした改正土壌環境保全法が2015年3月25日から施行される予定です。これは、2012年に下された憲法裁判所の憲法不合致決定の後続措置で、当時憲法裁判所は、(1)土地所有者に何の免責事由及び責任制限手段も置いていないこと、(2)土地譲受人に譲受時期に関係なく無制限的な浄化の責任を課したのは違憲であるという決定を下したことがあります。
|
|
|
|
改正法は、憲法裁判所決定の趣旨を反映し、「土壌汚染が発生した土地を所有していた、または現在所有している者」に対し(1)免責範囲を拡大する一方、(2)浄化責任が認められる場合には、一定の限界を設定してその限界を超える費用は政府の支援を受けられるようにしました。
|
|
|
|
改正法が施行されれば、「土壌汚染が発生した土地を所有していた、または現在所有している者」のうち次のケースに該当する所有者は免責されます。
|
|
|
|
1996年1月5日以前に当該土地を譲渡・譲り受けた場合:土壌汚染が発生した土地を過去に所有していたことがあった者でも、その土地を1996年1月5日以前に譲渡してそれ以上所有しなくなったか、譲渡したのはその後でも最初に土地を所有することになった時点が1996年1月5日以前であれば免責されます。また、土壌汚染が発生した土地を現在所有している者でも、土地を譲り受けた時点が1996月1日5日以前であれば免責されます。
|
|
|
|
土地を譲り受けた当時、土壌汚染事実に対し善意であり過失がない所有者:所有者が譲り受けた当時、土壌環境評価を受けて汚染の程度が憂慮基準以下であることを確認していれば、善意・無過失と推定されます。
|
|
|
|
土地を所有している間に土壌汚染が発生したが、土壌汚染発生に帰責事由がない所有者:土壌汚染の原因となった当該土地上の土壌汚染管理対象施設の所有者は免責されないのに対し(一定の場合、費用支援を受けることはできる)、その施設の敷地である土壌汚染が発生した土地の所有者は、土壌汚染の発生に自身の帰責事由がないということを立証して免責を受けることができます。
|
|
|
|
上記の各ケースに該当される場合にも、1996年1月6日以降に土壌汚染を発生させた者、または汚染の原因となった施設の所有者などに土地を賃貸するなどにより土地使用を許諾した場合には免責されません。
|
|
|
|
一方、次のケースに該当する「土壌汚染が発生した土地を所有していた、または現在所有している者」は、免責されはしなくても、土壌浄化などにかかる費用の全部または一部の支援を政府から受けることができます。
|
|
|
|
2001年12月31日以前に土地を譲受・譲渡した者で、土壌浄化費用が土地価額を超える場合
|
|
|
|
2002年1月1日以降に土地を譲り受けた者で、土壌浄化費用が土地価額及び土地から得た、または得られる利益を超える場合: 「土地から得られる利益」には、土壌浄化によって土地の価額が増加する場合の地価上昇分のような反射的利益が含まれます。すなわち、このような地価上昇分など土地から得た、または得られる利益の範囲までは責任を負わせ、それを超える費用に対しては支援を受けられるように規定しました。
|
|
|
|
上記のように規定が整備されることで、土地浄化の責任の分配に関連して免責事由の主張、それに基づく求償の範囲の確定などの紛争が増えると予想されます。したがって、改正法の施行後に土地を売買しようとする当事者は、関連資料を取引の初期段階から準備し、これに備えなければなりません。
|
|
|
|
特に、買取人(現在の土地所有者)は、譲受時点に土壌環境評価を受けて汚染の程度を確認し、土壌汚染に対し善意・無過失であることの推定を受けて免責されるようにしなければならなりません。しかし、現行法と異なり、改正法の施行後には、上記の推定が翻意して浄化責任を負う可能性があるという点に注目する必要があるため、買取人としては従来よりさらに綿密な準備をする必要があるとみられます。さらに、免責事由が認められず買取人が浄化責任を履行した場合、従来の所有者である売渡人にその費用に関して求償権を行使する方法が考えられ、この場合、売渡人の免責事由の存否及び帰責の程度を争わなければなりません。
|
|
|
|
|
|
メインページ一覧
|
|
|
|
|
|
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|
詳細については、幣事務所のホームページをご覧下さい。
|
|
|
|
|
|
|
|