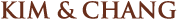|
|
|
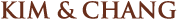
|
|
Newsletter | June 2014, Issue 2
|
|
|
|
|
|
|
人事・労務 |
|
|
|
2014年に施行される労働関係法規定の主な内容 |
|
|
|
勤労基準法、期間制及び短時間勤労者保護等に関する法律、派遣勤労者保護等に関する法律、男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律など各種労働関係法改正案が2014年現在施行され、または施行を控えています。
|
|
|
|
2014年度から新しく施行される労働関係法令の主な内容をご紹介します。
|
|
|
|
勤労基準法
|
|
|
|
2014年7月1日以降に出産する勤労者が、一度に二人以上の子女(多胎児)を出産する場合、出産前後の休暇期間が下記の通り延長されます(勤労基準法第74条第1項、第2項、第4項、付則第2条)。
|
|
|
| 現行 |
変更内容 |
- 出産前後休暇90日
- 出産後45日以上保障
- 有給休暇60日 |
- 出産前後休暇120日
- 出産後60日以上保障
- 有給休暇75日 |
|
|
|
|
妊娠12週以内と36週以降の女性勤労者が、1日の労働時間を2時間短縮申請する場合、使用者はこれを許可しなければなりません。ただし、1日の労働時間が8時間未満である勤労者に対しては、1日の労働時間が6時間になるように労働時間の短縮を許可することができます(勤労基準法第74条第7項)。使用者は、このような勤労時間の短縮を理由に当該勤労者の賃金を削減してはなりません(勤労基準法第74条第8項)。この制度は、常時300人以上の勤労者を使用する事業または事業場については2014年9月25日から、常時300人未満の勤労者を使用する事業または事業場は2016年3月25日から施行されます(勤労基準法第74条第9項)。
|
|
|
|
期間制及び短時間勤労者保護等に関する法律(「期間制法」)
|
|
|
|
既存の判例によると、短時間勤労者の超過勤労が1日8時間、週40時間を超えない場合(いわゆる「法内超過勤労」)、使用者はそれに対する加算手当を支給する義務がありませんでした。しかし、2014年9月19日から使用者は短時間勤労者の法内超過勤労に対し、通常賃金の100分の50以上を加算して支給しなければなりません(期間制法第6条第3項、付則第2条)。
|
|
|
|
2014年9月19日から、労働委員会は使用者の故意的または反復的な差別行為に対し、期間制及び短時間勤労者に発生した損害額の3倍以内で懲罰的性格の金銭的賠償命令を下すことができるようになりました(期間制法第13条第2項、付則第3条)。
|
|
|
|
2014年9月19日から、同一使用者の事業または事業場で一人の期間制または短時間勤労者に対する差別が認められた場合、同一条件にある勤労者全員の差別的な処遇が改善されるように、確定された是正命令の効力が拡大します(期間制法第15条の3)。
|
|
|
|
派遣勤労者保護等に関する法律(「派遣法」)
|
|
|
|
2014年9月19日から、派遣勤労者に対しても期間制法と同様に懲罰的賠償制度及び確定された是正命令の効力拡大制度が施行されます(派遣法第21条第3項、第21条の3)。
|
|
|
|
男女雇用平等と仕事・家庭の両立支援に関する法律(「男女雇用平等法」)
|
|
|
|
2014年1月14日から、事業主にも勤労者と同様に職場内セクハラ予防教育を受ける義務が課されます(男女雇用平等法第13条第2項)。
|
|
|
|
2014年1月14日以降に育児休職を申請した勤労者から、育児休職対象子女の範囲が現行の「満6歳以下の小学校進学前の子女」から「満8歳以下または小学校2学年以下の子女」に拡大調整されました(男女雇用平等法第19条第1項)。
|
|
|
|
メインページ一覧 |
|
|
|
|
|
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
詳細については、幣事務所のホームページをご覧下さい。 |
|
|
|
|
|
|