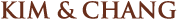|
|
|
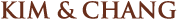
|
|
Newsletter | June 2014, Issue 2
|
|
|
|
|
|
|
訴訟 |
|
|
|
「独占規制及び公正取引に関する法律」上の「不当な共同行為」の認定基準に対する大法院判決 |
|
|
|
最近、「独占規制及び公正取引に関する法律」第19条第1項が禁止する「不当な共同行為」の概念とその判断基準に関する大法院判決が言い渡されました。
|
|
|
|
本件は、公正取引委員会(以下「公取委」)が焼酎の工場渡し価格の引上げに関連して「不当な共同行為」があったという理由で、事業者に対し是正命令及び課徴金納付命令を下し、これに事業者が公取委を相手取って上記処分の取消しを請求した事案でした。 |
|
|
|
大法院は、「不当な共同行為」とは、「不当に競争を制限する行為に対する合意」で、明示的な合意だけでなく黙示的な合意も含まれるという従来の法理を再確認しながらも、ここでいう合意とは、二社以上の間で意思連絡があることを本質とするので、単に上記規定の各号に挙げられた「不当な共同行為」と一致する外形が存在するからといって、当然合意があったとは認めることができず、事業者間の意思連絡の相互性を認めるだけの事情に対する証明があってはじめて「不当な共同行為」が認められるので、その証明責任はそのような合意を理由に是正措置等を命じる公取委にあると判示しました。
|
|
|
|
対象判決は、競合会社の値上げの外形的類似性が存在する場合でも、そのような結果が他の事情によって発生したという十分な説明がある場合には、公取委に合意存在事実に対するより厳格な証明責任を求めたものと評価され得ます。本事案で、大法院は国税庁が焼酎市場で支配的な影響力を行使する事業者に対し、物価上昇率に達しない程度に値上げを統制してきたので、国税庁がこの事業者に対する値上げを承認する場合、地域ごとにこの事業者と競争する当該地域の焼酎企業等がこれによって値上げをせざるを得なかったという原告の説明は、十分に説得力を持つとみました。
|
|
|
|
また、対象判決は、公取委が提示した値上げ論議の場とみられる社長団会議の存在事実及び事業者が競合会社の値上げ情報を交換してきた事実だけでは、合意を推断することはできないと判断しました。これは反対事実(即ち、外形的類似性が行政指導による結果であるという事実)が証明された以上、上記証拠の存在だけでは反対事実を排除するだけの証明があったとみることはできないと判断したものと解釈されます。 |
|
|
|
弊法律事務所は、事実関係及び関連法理に対する緻密な分析を通じて、事業者間の意思連絡に相互性があったとはみることのできない様々な状況を具体的に提示することで、大法院の破棄判決を引き出しました。
|
|
|
|
メインページ一覧 |
|
|
|
|
|
本ニュースに関するお問合せは、下記までご連絡下さい。 |
|
|
|
|
|
|
|
詳細については、幣事務所のホームページをご覧下さい。 |
|
|
|
|
|
|